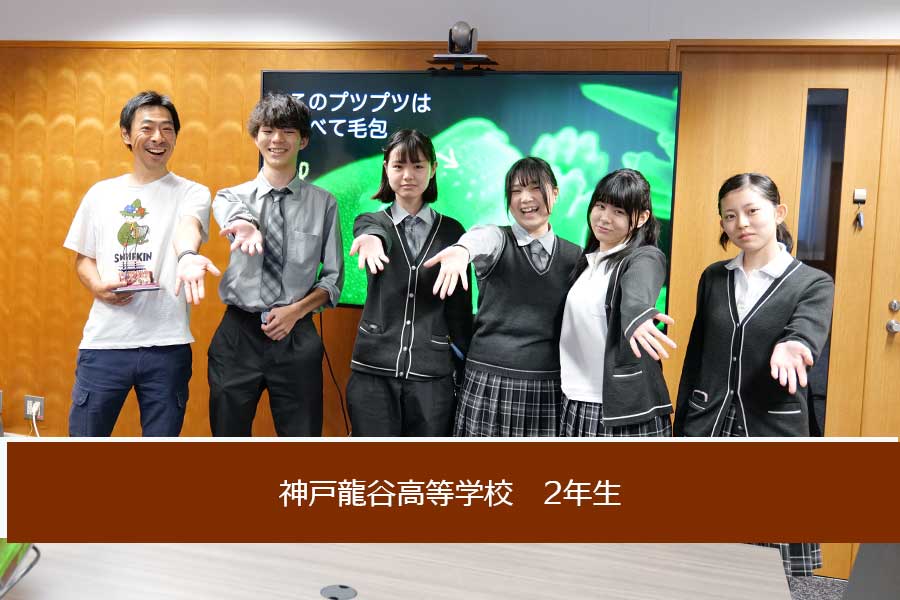指紋はどうやってできるんだろう?
藤原裕展(細胞外環境研究チーム チームディレクター)
✕ 神戸龍谷高等学校 2年生
日常生活で、私たちにとってスマートフォンは必要不可欠なものです。スマホのロック解除で指紋認証を何気なく行っていた時に、そういえば何で指紋は一人一人違っているんだろうと思った事がきっかけで、皮ふを研究している藤原裕展さんに話を聞き質問してきました。

皮ふはどんな構造なんですか?
皮ふは基本的に3層構造になっています。上から順に表皮、真皮、皮下組織です。そのなかでも表皮は再生能力が高く、損傷しても幹細胞のおかげですぐに元の状態に戻りますが、真皮は再生が難しく、傷が真皮にまで達すると、その部分の皮ふは、色や肌触りが変わる場合が多いです。
表皮は、未分化な幹細胞が増殖して、その子孫細胞が時間をかけて表皮の細胞になります。これを表皮細胞のターンオーバーといって、部位や年齢にもよりますが、だいたい40~50日で垢となって皮ふの表面から剥がれ落ちます。
鳥肌はなんで立つんですか?
鳥肌は、寒さや恐怖、感情の高まりに応じて皮ふに現れる生理現象です。科学的には、交感神経が刺激されることで、毛包にくっついている立毛筋という小さな筋肉が収縮し、毛が立つことで鳥肌が生じます。これは「立毛反射」とも呼ばれ、毛が逆立つことで体温を保持したり、動物が自分を大きく見せて敵を威嚇する役割があります。人間ではこの機能はほとんど失われていますが、寒さや恐怖を感じたときに反射的に現れます。鳥肌はまた、強い感情や音楽などによる「感動の震え」や「感情的な興奮」によっても引き起こされることが知られているんです。「鳥肌が立つ」とか「身の毛もよだつ」など、慣用句としても良く用いられます。私達は以前、この鳥肌を立てるときに活躍している立毛筋が、毛の幹細胞と相互作用しながら発生することを突き止めました。
アルビノ個体はなんで白いのですか?
アルビノ個体は、メラニンという色素を作る能力が欠如しているため、皮ふや毛髪、目の色が通常よりも淡くなります。これは「チロシナーゼ」と呼ばれる酵素の機能不全が主な原因です。メラニンは紫外線からの保護や視覚機能の発達に重要であるため、アルビノ個体は紫外線に対する耐性が低く、視力に問題が生じやすいです。また、アルビノは遺伝性疾患であり、通常は潜性(劣性)遺伝子によって引き継がれます。動物のアルビノ個体は自然界では目立ちやすく、捕食者に狙われやすいことが多いため、野生では生存率が低くなることもあるんです。
なぜ私達はそれぞれ違う指紋を持っているんですか?
指紋については、2023年にイギリスで行われた研究があります。
生命現象には「反応拡散機構」という、物質間の反応とそれらの空間的な拡散に基づくパターン形成のしくみがあり、様々な体の模様や繰り返し構造を作り出しているのですが、それと関連しています。指の発生過程で皮ふの表面を伝わるシグナルの波が起こります。その波の凹凸パターンに従って皮ふに指紋の基になる凹凸ができるのですが、その波のパターンが個人ごとに違うので指紋は一人ひとり違う模様をしています。
反応拡散系でいちばん有名なのは『チューリングパターン』という自発的に生じる空間的パターンです。チューリングパターンの最も分かりやすい例を挙げると、シマウマの模様です。シマウマ達は個体ごとに模様が違っていて、シマウマは群れの仲間たちをこの模様の違いで見分けていると言われています。
チューリングパターンとはイギリスの数学者アラン・チューリングによって理論的存在が示された自発的に生じる空間的パターンの事です。例えばAとBという2つの物質があったとします。AがAとBの産生を促進し、BがAの産生を阻害します。次に、Aはゆっくり拡散し、Bは速く拡散する性質があると、時間経過に伴って生じるこのAとBの反応と拡散の進展によって、場所ごとにAとBの存在量が変わり、その量比が周期的な縞模様や水玉模様を作り出します。指紋でもこのチューリングパターンがみられ、この波を起こす皮ふの形、つまり反応系の場の形が人によって異なるため、1人1人の模様が変わっているそうです。なので、スマートフォンの認証に指紋を使うことができるんですね。また、私が研究している毛包ができる位置の空間パターンも、反応拡散機構によって形成されることが15年ほど前に明らかにされています。
皮ふと粘膜の違いって何ですか?
皮ふには最外層の角層がありますが、粘膜には角層がありません。角層は上皮細胞が最終分化した細胞からなるバリア層で、乾燥や紫外線、刺激物質などから体を守っています。また、皮ふにはもう一つ、「タイトジャンクション」とよばれる分子バリアがあり、これは細胞間で密にくっついていて水も通さないんです。ですから、皮ふの表面に塗ったコラーゲンなどの大きな分子は基本的には皮ふ内には届かず、注射などで直接入れる必要があります。一方で、油やアルコールは細胞膜を透過するので皮ふに入っていきます。湿布剤には、分子量が小さくかつ脂溶性をもつ薬剤が含まれていることが多く、細胞や細胞間の脂質を通って皮ふに入っていくので注射などで直接入れなくても効果を感じられます!
どうして皮ふについての研究をしようと思ったのですか?
高校を卒業してからは大学で薬学を学んでいました。そして、大学卒業の進路として製薬会社の営業の仕事が決まっていました。しかし、大学でやった卒業研究を通して研究することの面白さに気づき、大学院進学を決めました。また、最初から皮ふの研究をしていたわけではありません。最初は細胞外環境を構築するコラーゲンやヒアルロン酸といった細胞外マトリックスの研究をしており、その流れで幹細胞の細胞外環境に興味を持つようになりました。皮ふには幹細胞がたくさん存在し、幹細胞の研究モデルとしてとても優れていたため、皮ふを研究モデルとして選びました。そういった経緯があり、今でも皮ふの研究をしています。
 藤原チームディレクターの資料を覗き込む生徒たち
藤原チームディレクターの資料を覗き込む生徒たち
インタビューを終えて
指紋はどうやってできるんだろう?というのは普段、全く考えたことがなかったのですが、ふと疑問を感じるととても気になりました。そして、難しそうでしたが説明を聞いてみるととても分かりやすくて、興味深いテーマでした。指紋が人によって違うことは当たり前のように思いますが、実際にはとても奥が深いものでした。
取材・執筆
神戸龍谷高等学校 2年生
牛嶋太風、小田桐遼、塚田結心、萩原凛生、吉田花音